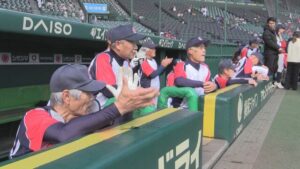【書評】『最終列車』/原武史・著/講談社/1980円
「車窓風景」というが、新幹線に乗ってそれをたのしむ人はいない。トンネルが多すぎる。 乗客はスマホばかり見ている。
柳田國男は「日本の車窓」について、書いている。「日本はつまり風景のいたって小味な国で、この間を走っていると知らず識らずにも、この国土を愛したくなるのである。旅をある一地に到着するだけの事業にしてしまおうとするのは馬鹿げた損である」
「小味」とは、変化に富むという意味で、日本の地形のありようからきている。しかるに「一分でも早い到着」をめざして発達してきた日本の鉄道は、電化し、複線化し、新幹線網をつくってきた。 今は、三泊四日で最高百五十万円などという「クルーズトレイン」を生み出した。これでは「中国的特色ある格差主義」そのものといわれても仕方がない。
その一方で、赤字ローカル線は自然災害を機に、廃止される。 「小味な車窓風景」を「発見」したのは外国人観光客であった。彼らが、川霧と古典的な鉄橋、桜から雪景色までの複雑な美に感動して乗りに行った結果、福島県と新潟県を山越えで結ぶ只見線は生き残った。
それは日本土着の「撮り鉄」、鉄道と春夏秋冬の風景を組み合わせた「写真歳時記」を愛する人々の海外版だが、「撮り鉄」のおおかたがヒマになった中高年男性で、孤独な印象なのに対し、海外版は年齢多様で陽気だ。
鉄道への愛着と政治学を結びつけた五十九歳の著者・原武史の「昭和」の記憶は鉄道とともにあって、いまも生彩を放つ。「車窓風景」だけではない。
鉄道は、漱石『三四郎』が鮮明にえがいたように、少年が社会と接触する場所でもあった。 「旅をある一地に到着する事業」の極北、リニア新幹線に対して著者が懐疑的なのは当然だろう。
引用元:https://www.news-postseven.com/archives/20220223_1728094.html?DETAIL